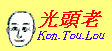第108回 [2005年12月10日] 【九鬼山〜菊花山】
−Photo & Report by H.Tanuma−
《画像をクリックすると大きな写真になります。保存は大きい方を!》
《サ-バ-容量に限度があり古い写真は抹消しなければなりません。保存は早めに!》
コ−ス=JR新宿駅[8:14]〜(ホリデー快速)〜富士急禾生駅[9:46]〜
〜弥生峠[10:50/11:00]〜九鬼山(970m)[11:25/11:40]〜札金峠[12:15]〜
〜704m峰[12:30/13:20]〜馬立山[13:40]〜沢井沢ノ頭[14:00]〜
〜菊花山(644m)[14:40/14:55]〜大月「よしの湯」[15:35]
2年前余り前⇒(2003年8月2日)に引き続き、予定通り【九鬼山〜菊花山】へ行ってまいりました。駅から直接登ることができ、下山も直接、大月の銭湯「よしの湯」に下りられるという大変便利なコースです。人気が高い九鬼山は当然としても、昭文社の「山と高原地図」にはルート表示がない「沢井沢
ノ頭から菊花山、大月市街」に通ずるコースも、我々以外に3パーティ、11名が踏破するほどポピュラーなところ。道も道標もしっかりしており、何れは昭文社「山と高原地図」にも記載されるものと思われます。
久しぶりに乗車した「ホリデー快速河口湖1号」は三鷹駅〜八王子駅では乗車率100%を超える盛況ぶりですが、高尾駅を過ぎるとぽつぽつと減り、富士急行線に入ると凡そ半分以下。禾生駅で下車したのは10数名、その殆どは登山者であり、そのまた殆どが九鬼山を目指します。今日も願ってもない快晴。気温は禾生駅で6℃。国道139号線から右に折れ、二手に分かれる登山道の右手を選択。杉山「新道」とありますが、しっかりと踏まれたかなり古い道のようです。弥生峠、別名「リニア見晴台」までは登りやすい九十九折りの道。ここから九鬼山までは標高差220mの尾根道。木々の間から周囲の山々を眺めながらゆっくりと登ればいつしか九鬼山の肩に到着します。ここは富士山を真正面に望める見晴台として有名。逆光なのがやや残念。(冬の午前中に富士山を順光で望めるのは愛鷹山ぐらいでしょうが) 九鬼山はこの見晴台とはやや離れ、眺めも北東から西方に限定されていますが、雲取山や飛龍山まで
も同定できるほどのなかなかの眺望です。
札金峠へは薄ら寒いやや岩っぽい道を急降下し、途中から左にトラバース。これから先の季節、アイゼンが無いと、この下りとトラバースはちょっと肝を冷やすかも知れません。寒々しい札金峠から登り直すとまた日当たりの良い尾根に上がります。この先、馬立山を経て沢井沢ノ頭まではちょっとだけ気持ちの良い尾根道。我々の行くルートはここからまた北西方面へ急転直下、約200mの下り。更に一転して沢井峠からはまた100m以上の登り返しがあり、もう終盤と思う気持ちがあると結構この登りは長く感じます。
菊花山の山頂直下は風化した岩が現れ、なにやらどこぞの庭園の庭石で我が身が虫の寸法になってよじ登っているような錯覚に陥ります。山頂は噂通りの眺望で、まさしく360度の大展望。たかだか600mちょっとの山で此程の眺めを得られる山はそうはないと思います。眼下の大月の町並みがそれこそジオラ
マのように感じられ、鉄道模型ファンならずとも自作コレクションに加えてみたいと思うような景色!
眺めを充分に堪能して「よしの湯」開店に合わせてそろそろ下りようか、と言いつつ下り始めるとさすがに僅か300m足らずの下降で、あっと言う間に大月の街に到着。この手軽さも呆気ないようでもそれなりに便利。身体が温まりきらないうちに「よしの湯」入湯。今日も一番風呂でした。今回はこれで終わらず、汗を流した後に甲州街道を西へ花咲集落まで少々遠征し、「竹馬」の甲州名物「ほうとう」(1,250円)を食しました。この季節、これがまたグー!
本日の実働時間:4時間11分
本日の累積登高差:1,041m
本日の踏破距離:12.9km
|
《写真の上にマウスを乗せると画像NO.が出ます! クリックすると大きなサイズに! 》
写真左から【01】禾生駅から登山口に向かう途中にある古い水道橋。まだ現役
【02】登山口から見る南大菩薩連山。手前はリニアモーターカー実験線。
【03】この登山口では2つのコースがあり、我々は右の杉山新道を選択。
【04】尾根に上がったところが弥生峠。「リニア見晴台」と看板があるがそれ程よく見えません。
【05】峠から久美山に登る途中から見る高川山と、奥にお坊山、滝子山。
【06】左から三つ峠山、本社ヶ丸、鶴ヶ鳥屋山。
【07】九鬼山手前の展望台。逆光で富士山が良く写ってません。
|







【08】九鬼山山頂で記念撮影。
【09】札金峠手前の分岐。
【10】ここが札金峠。かつてはここに分岐があったと記憶していますが今は殆ど廃道化。
【11】峠はこんな感じです。
【12】昼食の準備中。冬になるとなかなかお湯が沸きません。じっと待つ。
【13】昼食を終えて出発の準備。後ろのシルエットは九鬼山。
【14】馬立山に到着。眺望は良くありません。
|







【15】沢井沢ノ頭直下、菊花山の看板があるところが神楽山へ続く道との分岐。
【16】あれが御前岩でしょうか。奥は大桑山。
【17】沢井峠からの登り返しは結構しぶとい。
【18】菊花山頂からの眺め。遠くに今倉山が顔を出しています。
【19】こちらは南大菩薩連山。左端は滝子山、右端は雁ヶ腹摺山。
【20】中央奥は御正体山、その左手に九鬼山が微かに見えてます。
【21】百蔵山と扇山が仲良く並んで見えます。
|







【22】岩殿山。武田勝頼を見放した小山田信茂の居城があったところ。
【23】山頂での証拠写真。
【24】山頂から見る大月市街のパノラマ。よく見ると「よしの湯」の煙突が中央やや右上寄りに!
【25】大月の街に下山。薄井さんメール中。
【26】今日の目当てはこの店「竹馬」。駅からちょっと遠いですが行く甲斐はあります
【27】店の中。この雰囲気、気に入りました。
【28】目当ての「ほうとう」。出汁が良く利いていて美味。
|







【29】とっぷり暮れた大月市街。この看板、見覚えありますよね!
(単に通過しました!)
|