●中国の二胡はどれでしょう? 答え A
A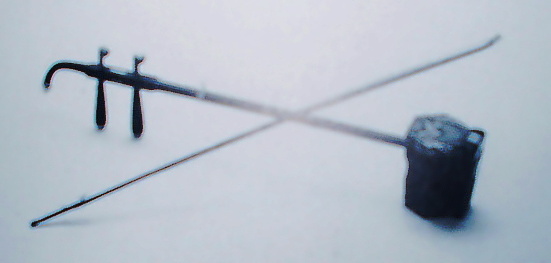
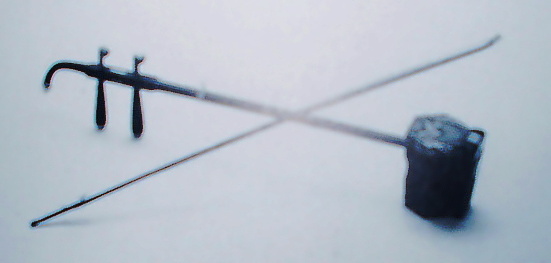
これが「二胡」です。弓が二本の弦の間に入っているのが特徴で,
弓の裏と表で2本の弦を弾き分けます。ここが魅力でありかつ難しいところ・・・
また写真では見にくいですけど,共鳴筒には蛇皮が張られています。
B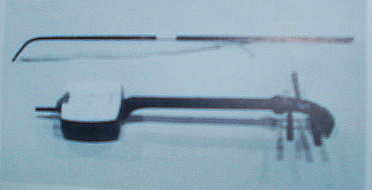
B
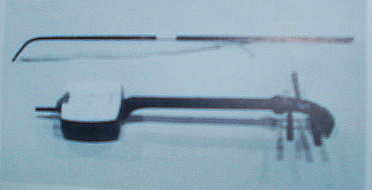
これは日本の「胡弓」。形態そのものは三味線に似ています。
弓はかんぜんに楽器から離れてます。
楽器の共鳴筒の下に突起があるのがおわかりでしょうか?
ここを軸に楽器本体を回転させて3本の弦を弾きわけるそうです。
C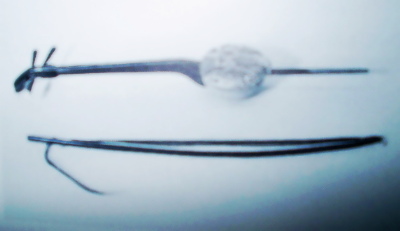
C
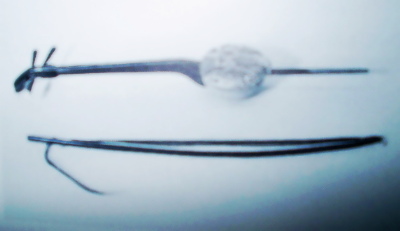
これは沖縄の「胡弓(くーちょう)」。
楽器を回転させて弾くのは本土と同じだけど,
一方で、共鳴筒に蛇皮をはるという点ではむしろ中国と共通してます。
→「もっと詳しいことが知りたい!」人は こちら へ(工事中)
●中国の琵琶はどっちでしょう? 答え E
→「もっと詳しいことが知りたい!」人は こちら へ(工事中)
●中国の琵琶はどっちでしょう? 答え E
D

これは日本の琵琶(雅楽琵琶)です。
日本の琵琶の特徴はばちで弾くということと,
首がかくっと折れ曲がっていることです。
このタイプの琵琶を曲頸琵琶といいます。
E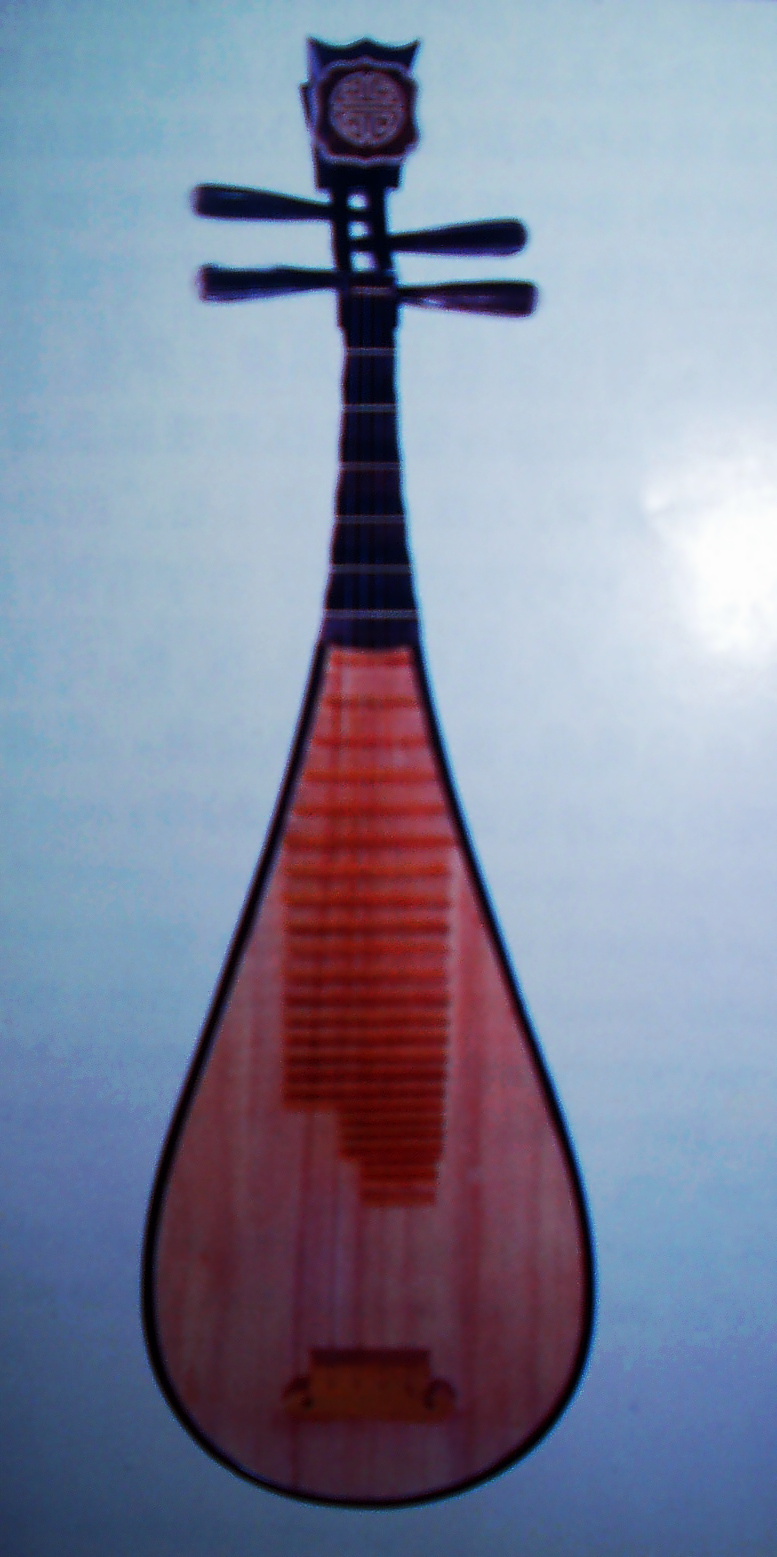
E
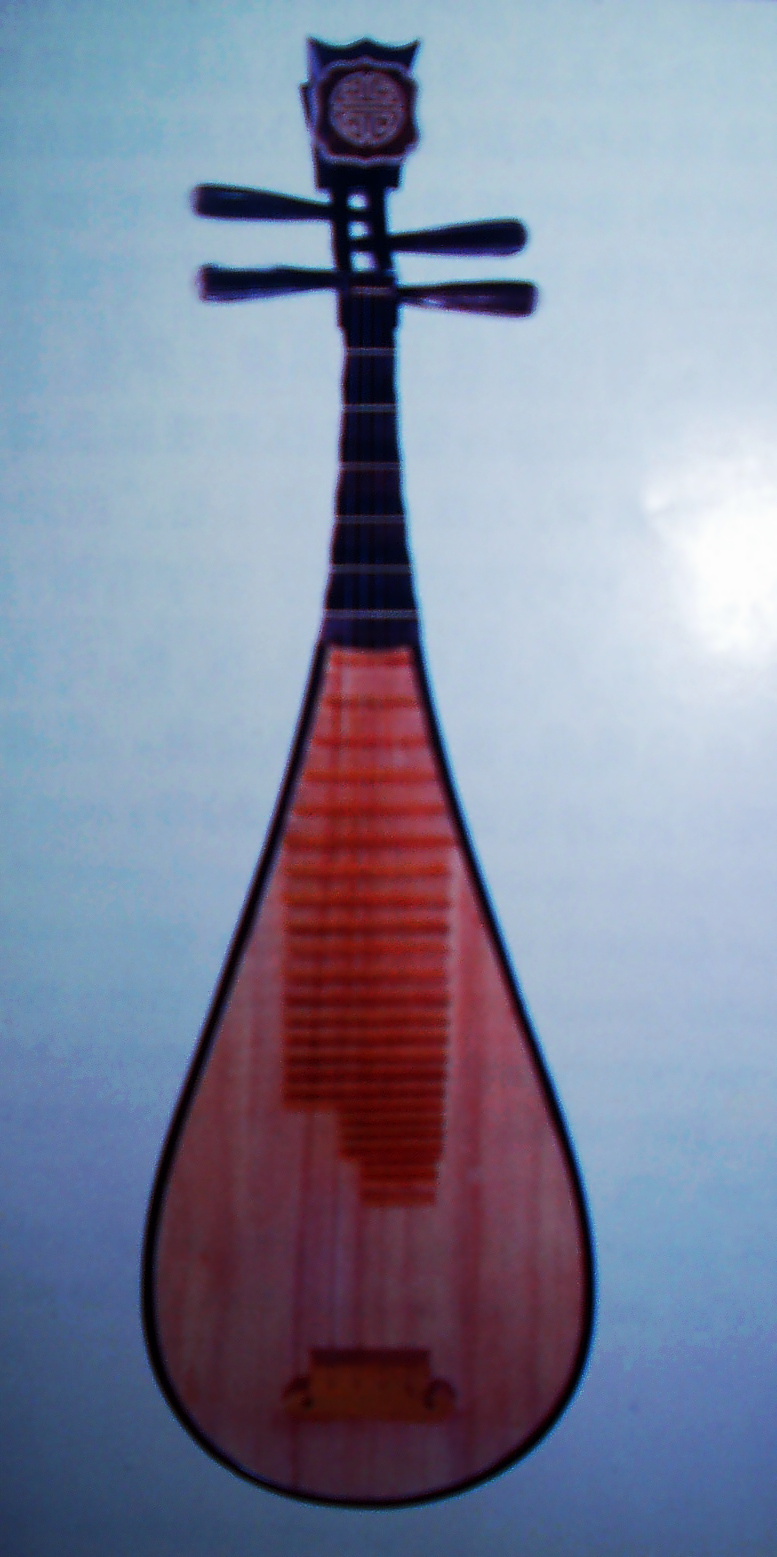
中国の琵琶はこちら。首が曲がってないので直頸琵琶といいます。
膝のうえでほぼ地面に垂直に立てるように構え,
指(orつけづめ)で弾くところが日本の琵琶と違います。
→「もっと詳しいことが知りたい!」人は こちら へ(工事中)
●次のア〜ウに当てはまる写真をF・G・Hから選びましょう。
ア 中国の「古琴」→F

→「もっと詳しいことが知りたい!」人は こちら へ(工事中)
●次のア〜ウに当てはまる写真をF・G・Hから選びましょう。
ア 中国の「古琴」→F

出典図録には幅広の方を左手にして載ってたんですけど,
『日本音楽大事典』の記載や図をみるとどうも反対みたいなんで,
180度ひっくり返しました。
下2つの楽器との大きな違いは琴柱(ことじ)がないことです。
イ 中国の「古箏」→G
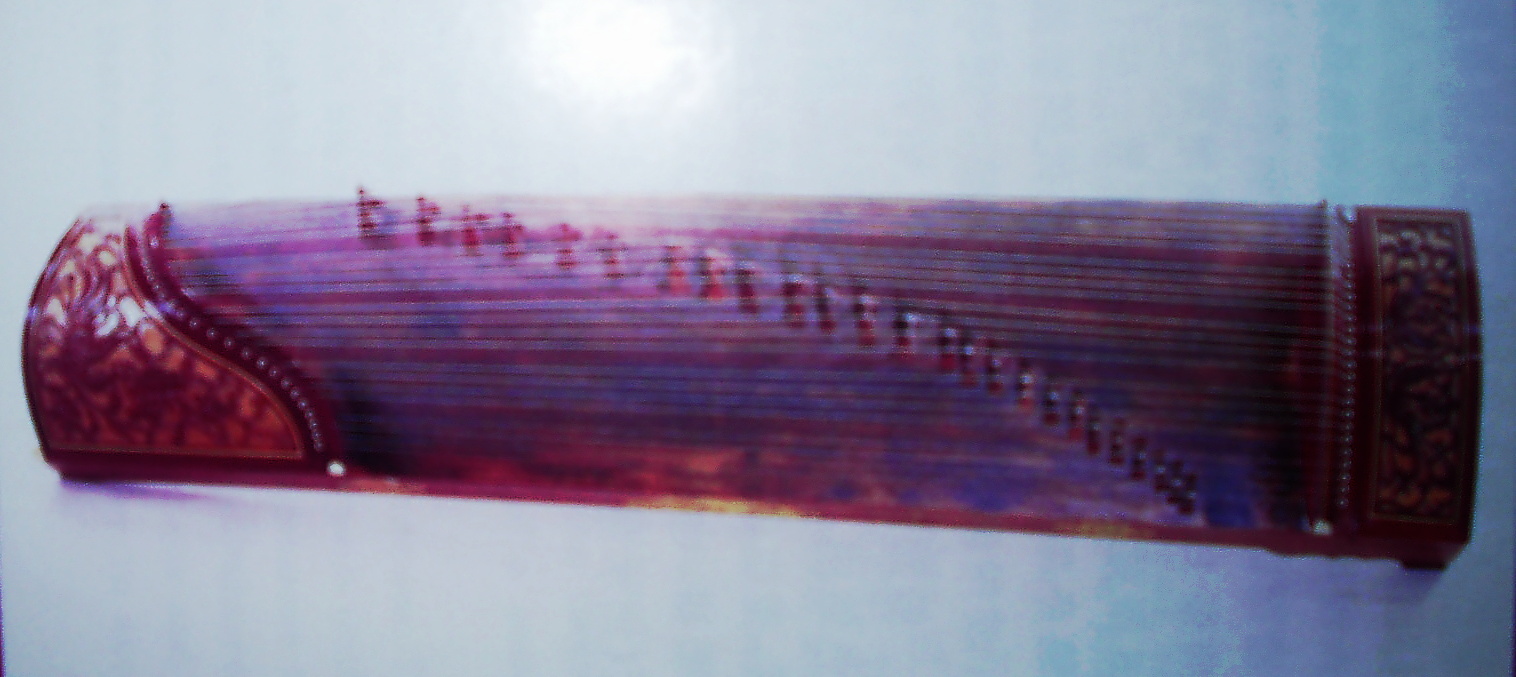
イ 中国の「古箏」→G
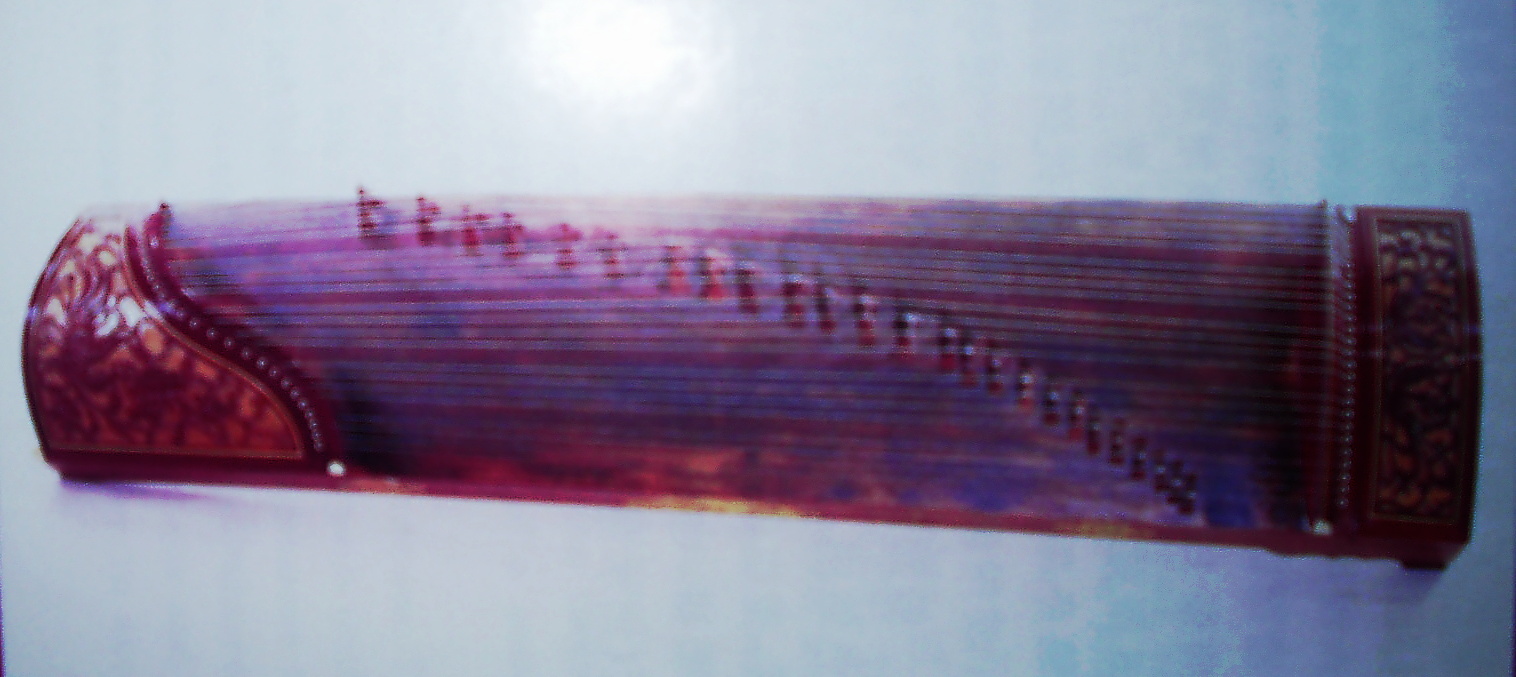
日本では二胡がブームですが,華人(華僑)の世界では,
むしろ古箏が圧倒的な人気を誇っているんだそうです。
中国の時代劇などでよくお姫様や美人の芸妓さん(?)が弾いてたり。
日本のお琴はこの古箏がルーツですが,中国のほうが演奏技法などを
どんどん変化させていったため,むしろ日本の弾き方のほうが
むかしの名残をよくとどめているんだとか・・
ウ 日本の「お琴」→H
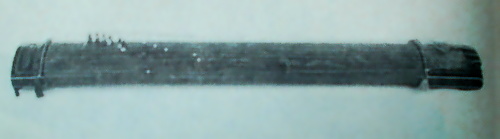
ウ 日本の「お琴」→H
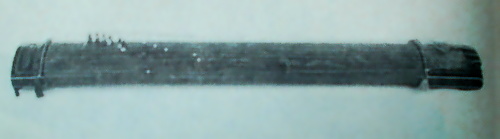
写真が見にくくてごめんなさい。
上に書いたとおり,「古琴」と「古箏」はまったく別ものなんで,
ほんとなら,日本のお琴は「お箏(?)」と言うべきなんです。どこかで
「箏」の字の下が「争」で縁起が悪いから「琴」にしたと聞いたことがありますが
ほんまにそうなら縁起をかつぐのもほどほどに,と言いたいですね。
→「もっと詳しいことが知りたい!」人は こちら へ(工事中)
出典:
→「もっと詳しいことが知りたい!」人は こちら へ(工事中)
出典:
A・D・G・H 応有勤『中国民族楽器図鑑』(上海音楽出版社 1997)
E 平野健次等監修『日本音楽大事典』(平凡社 1989)
F 小島美子『音楽から見た日本人』(NHK人間大学テキスト 1994)